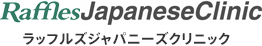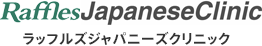義歯(入れ歯)を勧められたら
2025年9月9日シンスプリントと疲労骨折
2025年9月23日今回は体外受精の流れについてお話していきます。
体外受精と聞くと、「通院が多そう」「身体に負担がかかりそう」「費用も高いのでは」と感じる方も多いと思います。確かに、タイミング法や人工授精に比べると、準備や手順は多くなります。
ですが最近では、より身体に優しく、個々の体質や状況に合わせた柔軟な治療法が選べるようになってきています。特に「卵子の数より質を大切にする」考え方が主流になりつつあります。
治療の大まかな流れ
まずは月経が始まってから2―4日目の間に受診し、ホルモン検査や超音波検査を行います。その周期が体外受精に適しているかを確認し、問題がなければ卵巣を刺激する治療が始まります。
この卵巣刺激の方法にはいくつか種類があり、体質や年齢、ホルモン値、これまでの治療歴などに応じて最適な方法が選ばれます。
たとえば、薬を使わず自然に育った卵子を採る「自然周期」や、軽く薬を使って数個の卵子を育てる「準自然周期」、より多くの採卵を目指して注射などでしっかり刺激する「刺激周期」といった方法があります。
最近は、身体への負担を抑える自然周期や準自然周期を選ぶ方も増えてきていますが、一度に多くの卵子を確保したい場合は刺激周期が選ばれることもあります。特にシンガポールでは、刺激周期を基本とする施設が多い傾向にあります。
卵巣刺激を始めると、数回の通院または自己注射を行いながら卵胞の成長を確認していきます。月経開始からおよそ10日前後に診察を行い、卵胞の成熟具合によって採卵日が決まります。
採卵の2日前には、排卵を促すためのスプレーや注射を使用し、予定日に採卵を行います。
採卵当日は、パートナーの精子も必要になります。採れた卵子と精子を掛け合わせ、体外で受精させます。受精が確認できれば、受精卵を2~3日間、もしくは5~6日間育てていきます。
現在では、胚の育ち方を時間経過で記録できるタイムラプスインキュベーターなど、最新技術を使ってより質の高い胚の選別も行われています。
受精卵が順調に育ったら、子宮内に戻す「胚移植」を行います。移植の2週間後に妊娠判定を行い、妊娠の成立を確認します。
なお、最近では採卵直後に移植をせず、受精卵を一度凍結してから、次の周期以降に移植する「凍結胚移植」が主流となりつつあります。これは、採卵後の体調を整えたり、子宮内環境をよりよい状態にしてから移植したほうが、妊娠率が上がるというデータがあるためです。
最後に
体外受精は決して精神的にも身体的にも金銭的にも簡単な治療ではありませんが、選択肢が広がってきた今だからこそ、自分の身体や状況に合った方法で取り組むことができます。
わからないことや不安なことがあれば、遠慮なくご相談くださいね。
次回は「凍結胚移植における自然周期とホルモン補充周期の違い」についてお話しする予定です。
医師 長谷川 裕美子