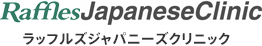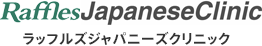からゆきさんを思う
2025年10月14日画像優位性効果
2025年10月28日子どもと大人の味覚の差は、ただの好みだけではありません。特に苦味に関しては、子どもの方が感受性が高いことがわかっています。これは、生き物が有毒なものを避けるための防御反応だといわれています。大人になると味の感受性が鈍くなるうえに、経験を通して「食べられる」「おいしい」へと変化していきます。
私も子どものころ、ピーマンが大の苦手でした。ある夜、「食べきるまで席を立つな」と母に言われ、3時間かけて完食したことがあります。今では普通に食べられますが、これは味覚の変化だけでなく、あの「やりきった」という経験も影響しているのかもしれません。
シンガポールに来て、最初はダメだったドリアンも、何度かチャレンジするうちに食べられるようになりました。最初は「匂いが…」と思っていましたが、「せっかくだし、どんな味だろう?」と興味本位で口にしたのがきっかけです。義務感ではなく、興味から挑戦したことがよかったのかもしれません。最近では、シーズンになると友人と食べ比べを楽しむほどになりました。
心理学的にも、「体にいいから」「食べなきゃ」と思うより、「どんな味かな?」「別の調理法なら美味しいかも」と探る気持ちで食べた方が、脳の報酬系が働いて受け入れやすくなるそうです。つまり、「嫌いを克服しよう」と思うより、「味の冒険をしてみよう」と考える方がずっと効果的とのこと。
味覚は「成長に伴う変化」と「繰り返しの経験」で少しずつ広がっていきます。お子さんに対して無理強いはよくないかもしれませんが、少しずつ慣らしたり、成功体験を積ませたりする工夫は大切です。ちなみに私の母は人参が嫌いだそう。私が子どものころは、バレないようにしていたことを、大人になってから知りました。自分のことは棚にあげるんかい、と思いましたが、あのピーマンと格闘した3時間を見守ってくれた母には感謝しています。
まずは「一口だけ」。おとなも子どもも、小さな冒険を、ぜひ。
医師 高木 太郎