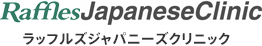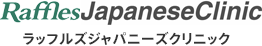赤ちゃんがほしい6 人工 授精
2024年12月3日腹部超音波でよくみる病気「肝血 管腫」
2024年12月17日私事ですが、先日「クレヨンしんちゃんRUN」というイベントに家族で参加しました。記念のメダルやしんちゃんとお揃いの黄色い幼稚園帽ももらえて大満足です。シンガポールでは今年、この他にも「ドラえもんRUN」「ちびまる子ちゃんRUN」というイベントもあったそうです。朝早くからセントーサ島の遊歩道を走る(または歩く)気持ちよさに加え日本のアニメがシンガポールに住む人々の健康に一役買っていることを知り、更に癒されました。
ところで、シンガポールに限らずジョギング愛好家の数は年齢を問わず増加傾向にあります。その一方で、オーバーユースによる障害も増えているようです。「ランナー膝」、「シンスプリント」、「疲労骨折」などは聞き覚えのある方もいらしゃるかと思います。個々の疾患についてはまた別の機会にお話をすることとして、ランニング障害の発生には自身の筋力や体の柔軟性など「身体的要因」の他に「環境要因」と「トレーニング要因」という3つの要因が関わり合っているということを今回のテーマにしたいと思います。
「環境要因」には路面の性質や傾斜などに加えランニングシューズの状態も含まれます。よく患者さんにお話させて頂くのは、アスファルトよりも柔らかい土やクッションのあるグラウンドを走るほうが地面から受ける負担が少ないということです。ランニングの着地時には地面から受ける反発力は体重の2~4倍ともいわれており、着地のたびに大きな負担が何度もかかることになります。そのため、大きな歩幅よりも小さな歩幅でランニングすることが推奨されます。
また、ランニングシューズも靴底がすり減ったものやインソールのクッション性が劣化したものをそのまま履き続けると、やはり膝や足に負担をかけることになります。しかも、踵の部分の靴底が外側もしくは内側に擦り減っているようなシューズでは着地のときの安定性が損なわれるため捻挫をしやすくなります。私は、500km以上を同じ靴で走ったならば一度靴を新調するように勧めています。シューズは普段からよくチェックしておくようにしましょう。
次に「トレーニング要因」ですが、急な練習量の増加、誤ったトレーニング方法の継続で運動器の障害が発生しやすくなります。ウォームアップやクールダウンも十分に時間を取って行いましょう。
自分にはどの要因が関係あるのかを考えることは安全で継続的なランニングのために大切です。
医師 長谷川 典子