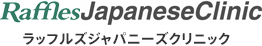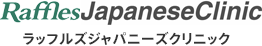紫外線と眼病1
2024年10月8日「最新ワクチン」RSウイルスワク チン「アレックスビー」
2024年10月22日その1では学校健診の意義とき胸部聴診の役割について述べました。今回は口の中の診察についてお話ししたいと思います。
健診に限らず、医師の診察と言えば口の中の診察が付き物です。大人も子供も、あのアイスの棒のような物を口に突っ込まれるのが苦手という方は多いと思います。あの棒の名前は「舌圧子(ぜつあつし)」といい、文字通り舌を押さえるための道具です。
医師も、患者さんがオエッ!っとなったりお子さんに泣かれたりするのは申し訳なく思いつつ、口の中から得られる情報は大変多いので、心を鬼にしてやっています。
健診よりも風邪などの急性期疾患のほうがイメージしやすいので、こちらを先に述べていきます。風邪のとき一番見たいのはのどの炎症所見です。この場合、「のど」というのは口蓋垂(いわゆる、のどちんこ)と扁桃(のどちんこの両脇にあるポコっとした部分)です。ここが赤くないか、ブツブツがないか、白苔や膿栓はないか、などをチェックします。手足口病、溶連菌など、のどの炎症所見から判断できる疾患もあります。鏡の前で口を開けていただくと分かると思いますが、道具を使わずに口蓋垂と扁桃を見せるには、相当大きく口を開けて舌を下に下げ、のどの天井を上げる必要があります。多くの方はそこまで開口できていないため、舌圧子を使用することになります。
健診のときは大体の方は元気なので、このような炎症所見はありません。しかし、お子さんの中には扁桃が大きめで、いびき、口呼吸、繰り返す扁桃炎などの原因になっている方がよくいます。また、のどの突き当たりの壁に、上から黄色いドロっとした痰のようなものが垂れてきている人がいます。これは「後鼻漏」といい、副鼻腔炎が原因です。
他にも下記のものをチェックしています。
・舌や粘膜の異常
・舌の大きさ、長さ
・唇や歯ぐきの様子
・歯並び、歯のお手入れ状況
・口臭の有無
時にはつらい口の中の診察ですが、スナイパーが一瞬で敵の数と位置を把握するように、医師もなるべく短時間で口腔内をチェックできるようにがんばっています。ぜひご自身でも喉の奥まで口を開ける練習をしてみてください。
医師 佐渡 めぐ美