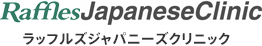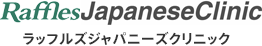眼科よもやま話 大人の視力回復治療 ―LASIKとICL―
2025年1月21日RSウイルスワクチン
2025年2月4日その1では胸部聴診、その2では咽頭の診察について述べました。その3では頭頚部の診察について述べたいと思います。顔まわりは他者に触られることに抵抗を感じる部分です。一方で、いろいろな情報を得られる部分でもあります。
一つ目は「目」です。診察の際、医師が目の下に親指を当て、下の瞼を引き下げていわゆる「あっかんべー」の状態にすることがよくあります。そうやって見える瞼の赤い部分を「眼瞼結膜」と言い、貧血のときはここの赤色が薄くなります。また、同時に白目の部分、「眼球結膜」も見ています。結膜炎のときに充血する部分ですが、肝臓の機能が悪いときにはこの部分が黄色くなる「黄疸」が見られるときがあります。他には、まれな病気でしか見られませんが、「青色強膜」(強膜は結膜の下層)という症状もあります。これらの膜に加えて、瞳もチェックします。瞳の部分は、真ん中の黒目を「瞳孔」、その周りの日本人だとやや茶色っぽい部分を「光彩」と言います。診察では、斜視がないか、瞳孔の奥に見える水晶体が白く濁っていないか、瞳孔の光への反応はどうか、等を見ています。
二つ目は「耳」です。耳の穴の一番奥には「鼓膜」が見えます。ここに穴が空いていたり、鼓膜のさらに向こう側に液体が溜まっていたりしないかどうか、チェックします。鼓膜を見る時は「耳鏡」という少し先のとがったライト付きの道具を使う必要があり、これがお子さんにはちょっと怖く見えてしまうことがあるようです。また、鼓膜は耳の部分(「耳介」と言います)を後ろに引っ張らないと見えにくいことが多く、この耳を引っ張られることにも抵抗があるかもしれません。医師は皆、なるべく早く正確に診察をと心がけておりますので、ご協力いただければ幸いです。
三つ目は「首」です。耳の下~あごの下、鎖骨周りにはたくさんのリンパ節があり、そこに腫れやしこりがないかどうかを触ってチェックします。また、のどぼとけの下あたりには甲状腺があり、ここにも腫れやしこりがないかを見て、触ってチェックしています。
顔~首周りは他者に触れられることが少ない部分で、先に述べたように診察に抵抗のある患者さんは多いかもしれません。医療者が「何のために、どこを見ているか」を患者さんにお伝えできれば、少しその抵抗感を和らげられるのでは?と思っています。健診のときはたいていすごいスピードで検査や診察が進むので、当日に診察の意味を説明することは難しいです。何かの機会にこのコラムが、健診を受ける患者さんの目に留まれば幸いです。
医師 佐渡 めぐ美