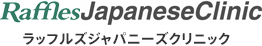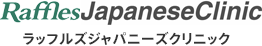マイクロスポリディア
2025年7月29日健康詐欺に騙されないための6つのポイント
2025年8月12日現代日本において、子育て中の保護者の方で「発達障害」という言葉を聞いたことのない人はいないのではないでしょうか。発達障害に対する人々の関心は非常に大きく、教育分野でも医療分野でも相談、診断、支援のニーズはとどまるところを知りません。このコラムでは、数回にわけて発達障害診療について考えていきたいと思います。今回は最初の項として、「病気を診断するということ」について述べていきます。
病気を診断する(病名をつける)のは医師の仕事の一つです。実際の診療では、診断のプロセスは連続的に行われていますが、よく見るといくつかのステップに分かれています。インフルエンザを例に、一般的な診断のプロセスと治癒までの経過を追ってみましょう。
ある日、Aさんは、発熱、咳、喉の痛み、鼻水の症状を自覚しました(健康問題発生)。
Aさんは近くのクリニックを訪れ、B医師を受診しました(医療機関受診)。
B医師はAさんから症状の詳細を聞き、胸の音を聞き、喉を見ました。周囲で流行っている病気、家族の症状などを確認しました。また、インフルエンザ検査を実施し、インフルエンザAに陽性反応が見られました(問診と診察、情報収集)。
B医師はAさんの症状の原因がインフルエンザウイルスAであり、症状は上気道(鼻―喉頭)にあると考えました(情報統合・解釈)。
B医師はAさんをインフルエンザと診断しました(診断)。
B医師はAさんに、病名、原因、症状、治療法、注意点などを説明しました(診断に関する対話)。
B医師はAさんに、抗ウイルス薬や解熱剤を処方しました(治療)。
Aさんは解熱しましたが、咳が残ってしまい、再度B医師のもとを訪れました。(フォローアップ。「問診と診察、情報収集」に戻る)
その後の治療を経て、Aさんのインフルエンザは治癒しました(結果)。
インフルエンザの場合は、このように短期間で比較的単純なプロセスを経て診断され、治癒に至ります。一方で、発達障害についてはどうでしょうか。私は、最も注意すべき点は、発達障害における特性が生まれつきのものであること、「治癒」という概念がないことだと思います。このような疾患は、ひとたび診断されると患者さんの生活や人生に大きな影響をもたらします。それゆえに医師は、しっかりとした診断プロセスを経て慎重に診断する(病名をつける)必要があります。実は、「発達障害」という言葉は、正確に言えば病名ではありません。また、今も様々なシーンで使われている有名な「アスペルガー症候群」という病名も、今は病名としては使用されていません。発達障害診療を考えるには、病名や疾患の定義を考える必要がありそうです。
次回、2では、発達障害/神経発達症の定義と歴史について述べたいと思っています。
医師 佐渡 めぐ美