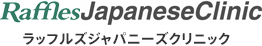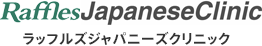大人の視力回復と老眼の克服―白内 障手術―
2025年4月29日百日咳
2025年5月13日学校健診について、胸部聴診、咽頭の診察、頭頚部の診察について述べてきました。
4は最後の項とし、検査の意義に触れながら健診の総括をしたいと思います。根本的に、他者に身体を見られる、触られることには抵抗や嫌悪感があるものです。それは生き物として当たり前のことです。診察はまさに「身体を見る、触る」ことなので、嫌がられて当然と言えます。ついでに言うと、問診(体の状態やそれに関わるエピソード、生活について医療者が患者に尋ねること)も嫌われがちです。プライベートな出来事や、時には排便排尿に関することまでお伺いするためです。
ときどき、「問診や診察をしなくても採血など検査をすれば解決するのでは」という声が聞かれることがあります。残念ながら、検査のみで分かることには限界がありますし、そもそも検査の項目を決めるために問診や診察は必須なのです。
まず、健診の検査と、何か症状がある場合の検査は意義が違います。健診の検査は「その年代によく起こる病気があるかどうか」をチェックする項目で構成されています。大人の健診ではイメージしやすく、例えば40-50代の健診であれば、高血圧・高脂血症・二型糖尿病・消化管の悪性腫瘍をチェックするための検査として、血圧測定、採血によるコレステロールや血糖値のチェック、バリウムや胃カメラが含まれます。一方で、症状がある場合の検査は、「その症状から考えられる病気があるかどうか、特徴的な変化があるかどうか」をチェックする項目で構成されます。例えば発熱→インフルエンザ検査、特定の食べ物を摂取した後の呼吸苦→アレルギー検査、という感じです。
症状がある場合の診断や検査に、問診と診察が不可欠であることは、上記からお分かりいただけると思います。では、健診についてはどうでしょうか。コラムその1では、健診の目的としてスクリーニングと健康教育を挙げましたが、やはりこのためには問診、診察が必要です。例えば、心臓の病気の一つである弁膜症は、心電図よりも胸部聴診で心雑音を聞き取ることが早期発見につながります。扁桃肥大、副鼻腔炎は採血に変化が現れず、問診や咽頭・頭頚部の診察で気づかれます。生活習慣病については、問診の内容(特に食生活と運動習慣)がそのまま健康教育につながります。健診もやはり、問診、診察、検査が揃って、いろいろな病気をチェックすることができるのです。
コラムその1からその4まで、患者さんに「嫌かもしれないけど我慢してください」という印象になっているのではないかと恐縮しています。医療者は仕事のほとんどが医療行為なので、患者さんが当然抱くであろう問診/診察/検査への抵抗に鈍くなってしまうことも否めません。医療者は患者さんの気持ちに配慮し、患者さんには「なぜこの医療行為が必要なのか」をコラムなどでお伝えして、スムーズで有意義な健診をみんなで目指していければと思います。
医師 佐渡 めぐ美